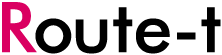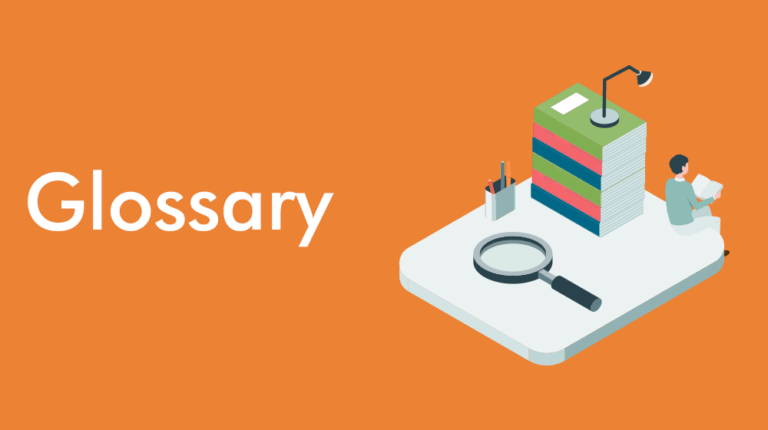ここでは特に初心者の方に向けて、ホームページ関連の用語についての説明をしてまいります。
CMS
「Contents Management System」の略です。ブラウザ上でテキストや画像の入力が出来るシステムで、簡単にホームページを制作することが出来ます。WordPressやMovable Typeなど、いくつか種類があります。
CSS
ホームページを作成するための言語の一つです。HTMLは主にホームページの構造を記述しますが、CSSはデザイン(文字の色や大きさ、余白など)を記述します。
ECサイト
「EC」は「electronic commerce」の略称で、意味は「電子商取引」となります。インターネット上などで通信販売を行うサイトの事をECサイトと呼びます。ショッピングカードなどがあるサイトは、ECサイトとなります。
FTP
ホームページのデータファイルを、サーバー上に送る時の規格を「FTP」と言います。CMSなどを使わない場合は、FTPソフトと呼ばれるソフトを使って、サーバーと通信を行います。
HTML
ホームページの構造、つまりメインとなる部分を記述するために使う言語となります。ホームページにとって必要不可欠な言語です。
OGP
XやFacebookなどのSNSにホームページのリンクが貼られた際に、ページタイトルや画像などが表示される仕組みです。基本的にホームページ側で設定を行わないと、画像などは表示されません。
SEO
「Search Engine Optimization」の略称で、日本では「検索エンジン最適化」という意味になります。Googleなどの検索エンジンに上位表示させるために行う対策となります。しかし検索エンジンで上位に表示されるための条件などは基本的に非公開ですので、推測や経験などに基づいて行われることになるため、確実に上位表示させる事は大変難しいです。
SNS
「Social Networking Service」つまり「ソーシャルネットワーキングサービス」の略称です。インターネット上で交流するためのサービスのことで、XやFacebookなどがあてはまります。
SSL
ホームページのサーバーとブラウザ間でデータの通信をする仕組みのひとつです。暗号化されているため、安全に通信を行うことが出来ます。アドレスの「http」のところが「https」になっていれば、SSLに対応しているという事になります。
UI
「User Interface」つまり「ユーザーインターフェース」の略称です。基本的には、ユーザーが商品やサービスなど利用する際におけるすべての接点のことになります。ホームページにおけるUIは、メニューやバナーなどの位置や場所などの機能性の事を指します。
URL
ブラウザのアドレスバーに表示されている「https://www.◯◯.com/◯◯.html」などの英数字のことになります。わかりやすく言うと、ホームページのデータが置かれている「住所」のことです。
WordPress
世界で最も多く使われているCMSになります。専門的な知識が無くても、ホームページを作成することが出来ます。
下層ページ
ホームページにおいて、トップページ以外のページになります。
キャッシュ
一度閲覧したホームページのデータを、一時的にブラウザに保存しておく仕組みです。二度目以降に閲覧したときに、データの読み込みを早くするというメリットがあります。
コーディング
HTMLを使って、ホームページを制作していく工程になります。
コンテンツ
「コンテンツ」そのものの意味は、なんらかの媒体を通して提供される情報などの事を指しますが、ホームページにおいては、そのページに掲載される内容全般のことになります。
サーバー
インターネット上にあり、ホームページのデータが置かれている場所のことです。ホームページを作る上では必須の物になります。
スマートフォン対応
スマートフォンからホームページを見ることが出来るようにする作業です。パソコンとスマートフォンでは、表示できる画面サイズが違うので、このような作業が必要になります。
スライドショー
トップページなどに良く見られる物で、画像が数秒起きに切り替わる物です。閲覧者の目を引くことが出来ますが、あまりに画像が多いと最後まで見る時間がかかってしまいます。
ソース
ホームページにおいては、ブラウザなどを通さないHTMLがそのまま記述された状態のファイルの事を言います。
導線
閲覧者の視線を誘導するために必要です。ホームページの場合、商品ページあるいはお問い合わせページに上手く誘導するための導線を作るのが大切になります。
トップページ
ホームページを開いた時に、一番最初に表示されるページの事です。住宅で例えれば玄関、本で例えれば表紙や目次にあたります。
ドメイン
ブラウザのアドレスバーに表示されている「https://www.◯◯.com/◯◯.html」の「◯◯.com」の部分がドメインです。ホームページの「住所」といえます。ホームページを作る上では必須です。
ノーコードツール
CMSよりも更に手軽に、視覚的な操作でホームページを作ることが出来るツールです。「jimdo」や「Wix」「STUDIO」など種類が多くあります。基本的にはテンプレートを利用するため、デザインの自由度はそれほど高くありません。また場合によっては料金が必要になります。
ファビコン
ブラウザのアドレスバーに小さく表示されるアイコンの事です。
ブラウザ
ホームページを閲覧するためのアプリです。古くは「Internet Explorer」や「Netscape」などがありました。現在では「Microsoft Edge」「Google Chrome」「Safari」など、いくつも種類があります。
ブログ
ホームページを簡単に作れるシステムなどを利用して作成した、個人的な日記や記録のことを言います。
ホームページ
一般的にいう「ホームページ」は本来は「WEBサイト」が正式名称です。「ホームページ」はそのトップページの事を指していました。しかし今ではあまり区別されません。
メールフォーム
ホームページの管理者に向けてメールを送信するための仕組みです。直接テキストを入力したり、いくつかの項目の中から情報を選び入力したりする事が出来ます。単純にメールアドレスを掲載するよりも利便性と安全性が高いのが特徴です。
モバイルフレンドリー
ホームページがスマートフォンやタブレットなどからも、見やすく使いやすくなっている状態を指します。特に近年はスマートフォンやタブレットからホームページを閲覧する人も多いので、モバイルフレンドリーである事が高く求められます。
ユーザビリティ
ホームページの使いやすさです。例えば欲しい情報がすぐ分かるようになっているか、メニューボタンが使いやすいか、データが重すぎないか、などなどです。
ランディングページ
特定の商品やサービスなどに特化したページで、問い合わせや購入などを促す事に特化したページです。企業ページなどからは独立しており、縦に長くなっているのが特徴です。
レスポンシブ化
パソコンやスマートフォンなど、画面サイズが違う複数の端末に応じて、ホームページのレイアウトが自動で切り替わるようにする事です。もともと携帯電話などのホームページはパソコンとは別に制作していましたが、二種類のページを作ることになるため、手間などがかかっていました。レスポンシブ化を行えば、基本的に一つのファイルで複数種類の端末に対応できるようになり、コストの削減になります。
ワイヤーフレーム
ホームページのデザインを作成する前段階の、大まかな形でのレイアウト案になります。いわば設計図のようなものですが、ある程度のイメージが固まっているのであれば、作る必要はありません。